
みなさま、こんにちは!チェヨンです!
貯金が貯まらない!!!という皆さま。
いらっしゃいますか?
これまでいろんなブログやYouTubeで、「貯金する方法」について調べたけど、全然貯められない!と失敗が続いている方。
特に一般企業にお勤めの20代、30歳前後の方は年収350万円~400万円と満足に貰えておらず、生活も大変ですよね。
今日は、年収400万円のサラリーマンとして年間150万円以上貯金をしていた私が、シンプルな方法を伝授しましょう。
投資に関する情報やプライベートな発信は日々Twitterに更新していますので、是非フォローお願いします!
Follow @chaeyounginvest貯蓄とは?貯蓄・貯金・預金それぞれの「違い」を知ろう!

お金を貯めることを表す言葉って、色々ありますよね!
私は20代、年収400万円時代に、毎年150万円以上を貯金し続け、無理をすることなく20代で1,000万円の貯蓄に成功しました。
年間150万円を貯金するには、がむしゃらにやっても続きません。
先ずは言葉の意味を知ることが重要だと思います。

中でもよく使われているのは、「預金」「貯金」「貯蓄」の3種類でしょうか!
預金:金融機関にお金を「預ける」こと
まず預金。これは、簡単にいうと銀行に預けてるお金のこと。
毎年雀の涙に近い「利子」が振り込まれるのはご存知ですよね!
このお金がなぜ振り込まれるかというと、あなたが銀行に預けたお金で、銀行は資産運用を行います。
要は、「お金貸してくれてありがとうな!おかげでオレたち資産運用して儲かったわ!これ、ほんのちょっとだけど受け取ってくれよ!笑」という意味合いで、年利0.0001%レベルの、マジでちょっとだけの利子が配られるのです。

後述しますが、銀行は人を馬鹿にしています。
例えば、あなたが預金している100万円。それを1年間運用し、銀行側に20万円の利益が出た時、100万円の運用資金を出したあなたに支払われるのは、なななんと「100円」www
私ならグーパンチですね。
預金しておけば利子で稼げる時代は、バブル崩壊と共に終わりました。
貯金:お金を貯めることを広義的に表現したことば
2つ目は、貯金。貯金には、先ほどお話した「預金」も含まれます。
銀行に預けるだけでなく、家の貯金箱にお金を入れるのも貯金、へそくりを隠し持つのも貯金です。

年収400万円のサラリーマンが年150万円を貯金するためには、本当にこれだけ覚えておけば大丈夫です。
「お金は、使った分だけ無くなる。」
カンタンでしょ?
貯金できなーい!って言ってる人は、結局自制心が無いから使っちゃってるんですよね。
本気で貯めようと思ってないだけ。
貯められる人間、貯められない人間、その差は、お金を使っているか使っていないか。
小学生でも理解できるこんな内容を、なぜ説明しなければいけないのか。
貯金が苦手な人は、いつまで経ってもこれが理解出来ていないからですね。

年間150万円を貯蓄できている年収400万円のサラリーマンは、友達と無駄に飲みに行ったり、休日は暇だからパチスロ打ちに行ったり、お金無いのにウーバーイーツ、Walt、menu、出前館を利用したり、サブスク無駄に登録していたり、不必要に広く家賃の高い物件に住んだり、車を所有したりはしないものです。
貯蓄:金融資産を含む総称
3つ目は貯蓄。貯蓄とは、株式や保険等、現金ではない資産も合わせた財産のことです。
貯蓄は、以下のものを全て含みます。
預金 ・普通預金
・定期預金・積立預金
貯金(預金も含む)・タンス貯金・へそくり・500円玉貯金
貯蓄投資 ・国債・社債・積立投資・株式投資・不動産投資・生命保険・年金保険・養老保険
「貯蓄」は、「預貯金」よりもさらに大きな概念であることがわかりますか?
「元本保証で、なくならないように置いておくこと」が「預貯金」の目的だとすれば、
「貯蓄」の目的は、「今よりも増やすこと」となります。

つまり、資産形成および資産運用と強く結びつくのは、実は「預金」や「貯金」ではなく、「貯蓄」なのです!
さあ!知識は付いた!後はどうやって貯蓄するか?

額面年収400万円のサラリーマン。所得税や住民税、厚生年金保険料が引かれた(控除された)手取り収入は約330万円となります!
ボーナスに関しては毎月の収入に落とし込んだ形で計算をしますと、
330万円÷12カ月=27.5万円
毎月の収入は27.5万円となります。
年間150万円の貯蓄をしようと思うと、
150万円÷12カ月=12.5万円
毎月12.5万円のお金を残すことが出来れば、1年で150万円の貯金が可能という計算となります。

27.5万円‐12.5万円=15万円
1か月の支出を15万円以内に収めれば、年間150万円の貯蓄が達成されるのです。
毎月15万円で暮らすと考えれば、簡単そうですよね?
しかも、この計算には節税対策を全く考慮していないのです。
毎月12.5万円を先取り貯蓄し、死んでも使わない生活をするだけで、絶対に達成は可能です!!
月15万円で生活し続けるポイント
人は誰しも、生活するうえで「譲れるポイント」と「ゆずれないポイント」があるものです。
自分にとって「ゆずれないポイント」の支出まで節約をしてしまうと、絶対にその生活は不幸なものとなり、続きません。月15万円という枠内で、節制するポイントと、贅沢するポイントを事前に決めましょう。

私で言うと、極論ですが、家は安くてボロボロでも構わないけれど、食費と交際費にはお金をかけたい!と考えています。
そして何よりも大切なのは、年収が上がったとしても、生活レベルを上げないこと。
これを守ることで、年間200万円~の貯蓄も可能となり、あなたの未来が輝くことでしょう。
年収400万円におすすめの節税対策

先ほども話しましたが、年収400万円の手取り額は約330万円となります。
所得税や住民税、厚生年金保険料などが控除されることで約70万も手取り額が下がります。
月15万円で生活するのはやっぱりキツイ!!!というアナタ。
年収400万円の人におすすめの節税対策を紹介します。

ふるさと納税、iDeCo、つみたてNISAなど、どれも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?これは投資をしたことの無いサラリーマンの方でもおススメの節税対策となります!
それぞれの制度の仕組みを、正しく理解しておきましょう。
■ふるさと納税
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付ができる制度です。
寄付をすれば、返礼品(地域の特産品など)がもらえるので、多くの人に知られている制度ではないでしょうか。
ふるさと納税のポイントは、寄付したお金が一定額まで税金から控除される点です。寄付金から2000円を引いた額が控除されるので、仮に3万円のふるさと納税をすれば、2万8000円が住民税や所得税から控除されます。

ふるさと納税が大好きな私が選んだ、超おススメの返礼品を下記のブログにまとめています!何を買えばよいのかよくわからない方は、私のブログに書いている商品を選べばまず間違いないと思いますので、是非ご覧ください!
■iDeCo (個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金制度の1つであり、加入するかどうかは自分で決められます。ちなみに私は現在置かれている立場、仕事の都合で加入していませんが、数年後の加入を検討しています。
掛け金・運用益・給付を受けるときに税制上の優遇措置が受けられて、老後資金を無理なく貯めることができます。

鬼注意ポイント!!
※iDeCoで積み立てたお金は、60歳を過ぎるまで原則受け取れません。
年金を増やしたい、また老後資金を蓄えたい人に向いている制度になってます。
■NISA、または、つみたてNISA(小額投資非課税制度)
NISA、または、つみたてNISA(少額投資非課税制度)は、投資経験のない初心者の人でも始めやすいといわれています。
投資で得た配当金や分配金などの利益は、通常であれば20.315%の税金がかかりますが、
つみたてNISAなら非課税となるのです。
NISA口座を開設し、その口座内で購入した金融商品が非課税になること、年間投資額はNISAで年間最大120万円(非課税期間は5年:最大600万円を非課税枠で運用可能)、つみたてNISAで最大40万円(非課税期間は20年:最大800万円を非課税枠で運用可能)であることなどルールがあります。
つみたてNISAでの資産運用を検討している人は、制度を正しく理解してから挑戦しましょう。
おわりに
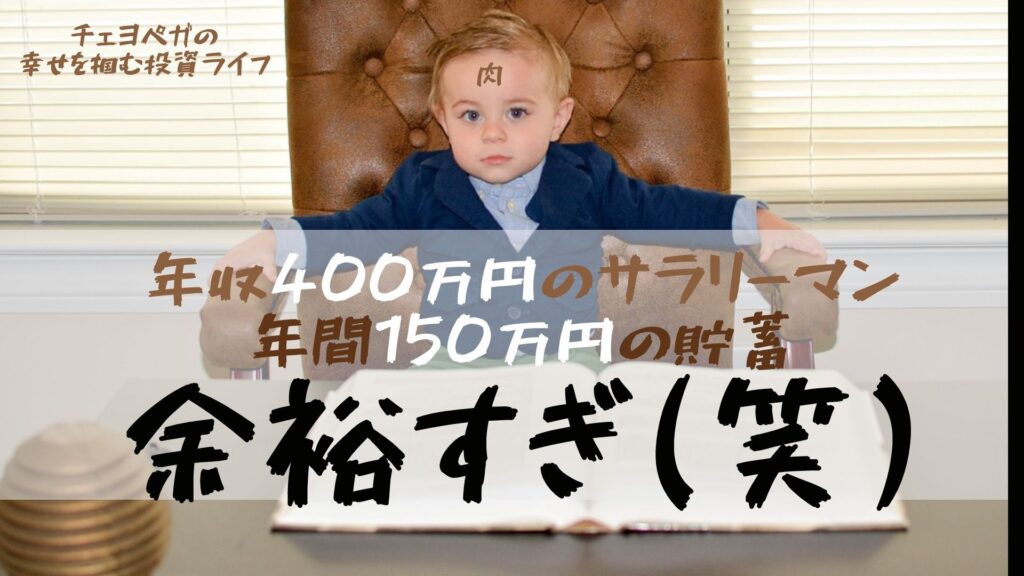
上記で話した節税対策をうまく活用すれば、毎月の支出が15万円以上になってしまったとしても年間150万円以上の貯蓄に成功する可能性が高まります!
また、どうしても支出15万円では生きていけない!という方は、副業で収入を増やすという方法もあります。
収入を増やすよりも今の支出を減らす方がカンタンなので、今回は支出を減らすことに重きを置いた内容となっていますが、収入を増やせるなら、それに越したことはございません。

私は現在、本業収入(メーカー営業マン)+資産収入(株式からの配当金、分配金)+副業収入(ブログ)で生計を立てています。本業収入の柱しかない場合、万が一のことがあった場合大変なことになるので、収入を分散させています。
ここまで読めば、もう年間150万円以上の貯蓄は約束されたものです。
- 先取り貯蓄したお金は死んでも触らない
- 月15万円で生活するために使うところ、使わないところを決める
- 節税対策に取り組む
貯蓄が増えれば、大抵の事はストレスを感じることなく過ごせます。
特に、貯蓄が1,000万円以上あると、例えば車だって、「買おうと思えば今日にでも買える。でも買わないー。」という風に、自分に選択権が与えられます。
まずは計画を練って、支出を見直していきましょう!

最後までありがとうございました~!
是非、下にある米国株ボタンのクリックをお願いしますー!





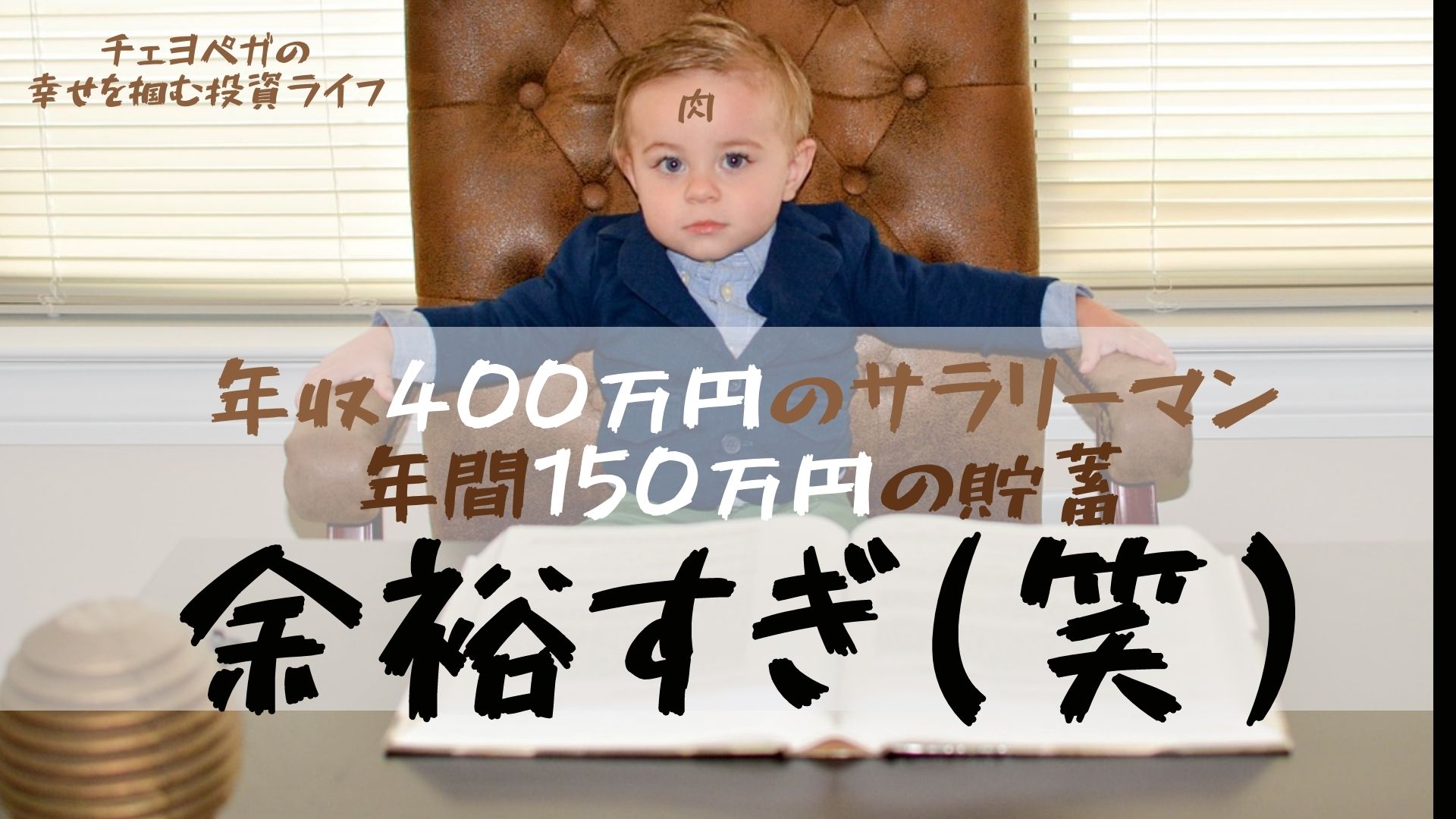


コメント